| 編集長コラム | ||
先進国日本の農水省の役割は… | 農業経営者 8月号 | (2001/08/01)
基本的にとは、大小様々な農業経営者自身の自助努力による経営改革なしには日本農業は救われないということ。そして構造政策の必要性である。
さらに言えば、お役人が考えるレベルの経営モデルや経営計画などということを現実の農業経営者に押し付けるような時代は終わっているのだ。現代の農業経営者たちはそんな無知蒙昧な愚民でもなく、そんなことは農業経営者たちや関連産業人の自助努力に任せておけばよいのである。直売所で野菜を売るオバアチャンたちを含めてマーケット(お客様)に気付いた人々が農業を変えていくのである。むしろ、行政や政治の過剰な干渉や指導こそが、農業界の改革すべき組織や商慣行を温存させ、農業改革のパワーを削いでいるとすら言うべきなのである。
本誌自身、読者と共にこうした取組みを通して感じてきたことは、前向きな農業経営者たちほど地域や既存の組織から、必要な情報や指導を得ることができないでいることである。しかしその結果 、彼らは地域や業種の異なる目線の揃う人々と強い共感で結ばれていったのだ。
これからの時代に農水省の役目として期待されていることは、これまで農民が市場社会に参加していくことを阻み、隔離してきた様々な障壁を取り除くこと。そして、未来から逆算する今日を作り出そうとしている農業経営者を励ますことであり、そのための情報提供であり施策である。
各地の農業経営者たちは、多様な形でその経営を発展させていくであろう。そこに、いまさら農水省が正解などを示す必要はないのである。それが先進国日本の農業の姿なのではないか。そして、直売所のバアチャンや行商で頑張る夫婦農家も大規模生産者もその可能性を差別 する必要などないのである。
海外農産物の輸入増大によって亡びていく産地や経営が成り立たなくなる生産者も出てくると思われる。急激な市況の変化に対応するための配慮は必要かもしれない。しかし、海外農産物の輸入増大が引き金になっているかもしれない経営危機とは、元はと言えば産地、そして彼の経営努力の問題ではないのか。怠慢な人物を救うために伸びる芽を摘むようなことは、もういい加減にすべきなのだ。むしろ、そうした脆弱な経営体質を許してきたこれまでの農業政策や農業利権の温存こそ問われるべきなのである。そして、仮に農水省の後ろ盾がなくとも、自らの永続性のために農産物消費に関わる業界人が『産地』ではなく『経営者』を探し出し、両者が食べる人々への共同の責務を追求すべき時代なのである。




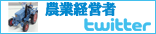


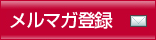
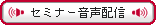

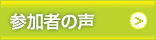

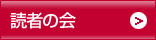
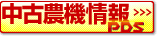
buy prednisone 40mg online - prednisone nz prednisone sale