| 編集長コラム | ||
若き農業経営者たちへ | 農業経営者 2月号 | (2000/02/01)
彼らの没年を列挙すれば、吉田松陰29歳(1830~1859年)、高杉晋作28歳(1839~1867年)、久坂玄端24歳(1840~1864年)、坂本竜馬34歳(1833~1867年)、木戸考允44歳(1833~1877年)、伊藤博文68歳(1841~1909年)、勝海舟72歳(1823~1899年)、井上馨80歳(1835~1915年)、山県有朋84歳(1823~1922年)などである。そして、吉田松陰がペリー提督の黒船で密出国を試みたのは23歳の時であり、高杉晋作が藩命を受けて上海へ渡ったのも23歳だった。
話は変わるが、筆者が農機具の業界雑誌の編集という仕事を通して農業関係の仕事を始めて26年になる。その間、たくさんの農家や農業にかかわる職業人たちに出会ってきた。現在の年齢で言えば、90歳位の方から20代まで様々な年代の人々である。同じ農家であっても経営作目や地域、そして自らの経営目標や立場の違いによりその考え方や意識には、同じ「農家」という言葉でくくられる人々の間にも大きな隔たりがあった。それは、本誌が言う「農家」と「農業経営者」との違いでもあった。その時代その時代に、それぞれの場所や立場で、困難や葛藤を抱えながら農業や地域の改革に取り組む人々に出会ってきた。しかし、ここ数年、40代、あるいは20代、30代の農業経営者の中に、それまでの世代とは異質の、息張ることもなく自然体で社会や歴史と向き合い、自然体で市場社会や世界を視野に入れながら自らの経営を創造し、未来に働きかける青年たちが育ってきているのを感じることが多い。
農業そしてわが国の形が第何回目かの開国の時代を迎えつつある中で、農業の世界にも新しい時代新しい世界で、たくましくそして伸びやかに、日本農業を担うにふさわしい歴史を受け継ぎ、新しい時代を作る世代が育ってきている。
もし、お手元に本誌が隔月刊だった頃の21号をお持ちの方がいるなら、その号の本欄を読み返していただけないだろうか。そこで、こう書いた。
たぶん歴史とは、ピサの斜塔のように傾いた螺旋階段を上っていく形の循環なのであり、それはやがて重力で転倒する。それが歴史の転換点なのである。そして、その傾いた螺旋階段の転倒とは新しい時代の始まりなのであり、その時から次の螺旋階段は始まるのだと。そして、人はやがて転倒する螺旋階段を後戻りすることを許されずに押し合い圧し合いしながら上っていき、ある者はその途中で足を踏み外し転落していく。しかも、その階段はあらかじめに構築されているものではなく、人が何もない中空に足を踏み出すことで新たな階段の一段ができていく。足を踏み出せない者に次ぎの一段は無いのだ。
僕が最近出会う若い農業経営者たちは、次ぎの一段も、階段が次ぎに転倒する方向も明瞭に見えつつ自信を持って足早に次々と足を踏み出しているように思える。彼らは「食べる人」のためにこそ農業に取り組む者たちであり、彼らに見えているのは「お天道様」と「お客様」なのだと思う。
そして、そんな若い人々に言っておきたい。君たちに改革の担い手としてのバトンを手渡すためにこそ、時代を切り開いてきたたくさんの無名の人々がいたことを忘れるべきではない、と。




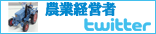


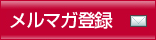
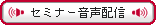

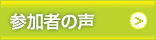

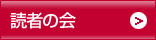
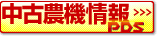
free online dating sites
online free dating service