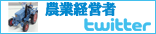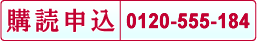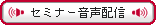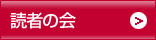農業経営者取材 [75]
- 新・農業経営者ルポ [47]
- スーパー読者の経営力が選ぶ あの商品この技術 [28]
- 叶芳和が尋ねる「新世代の挑戦」 [13]
農業経営者コラム [51]
- 激突対談・高橋がなり×木内博一 [1]
- 高橋がなりのアグリの猫 [26]
- ヒール宮井の憎まれ口通信 [14]
- 木内博一の和のマネジメントと郷の精神 [7]
- 幸せを見える化する農業ビジネス [5]
提言 [60]
- 視点 [60]
農業技術 [68]
- 大規模輪作営農のための乾田直播技術 [6]
- “Made by Japanese”による南米でのコメ作り [6]
- 乾田直播による水田経営革新 [23]
- 防除LABO [31]
農業機械 [23]
- 土を考える会 [1]
- 機械屋トラクタ目利き塾 [16]
- 機械屋メンテ塾 [6]
- 機械屋インプルメント目利き塾 [2]
農業商品 [8]
- 読者の資料請求ランキング [8]
時流 [287]
海外情報 [3]
| 農業経営者取材 | 新・農業経営者ルポ | ||
第45回草取りは、上手くなっては駄目なんだ | 農業経営者 3月号 | (2008/03/01)
【高松 求(茨城県牛久市)】
 1930年、茨城県生まれ。1947年、茨城県牛久市の高松家への婿入りをきっかけに、本格的に農業を始める。以後、茨城県を代表する農業経営者として多くの人々に影響を与えた。98年には、「『土の力』を引き出す米づくり、『豚の心』を読んだ飼養技術、『地域の教育』を重視した近隣の子供たちへの竹林の開放などユニークな活動を展開」などを理由に、山崎記念農業賞を受賞。引退した現在も、若い経営者たちや業界人、研究者にヒントを与えリードする指導者になっている。
1930年、茨城県生まれ。1947年、茨城県牛久市の高松家への婿入りをきっかけに、本格的に農業を始める。以後、茨城県を代表する農業経営者として多くの人々に影響を与えた。98年には、「『土の力』を引き出す米づくり、『豚の心』を読んだ飼養技術、『地域の教育』を重視した近隣の子供たちへの竹林の開放などユニークな活動を展開」などを理由に、山崎記念農業賞を受賞。引退した現在も、若い経営者たちや業界人、研究者にヒントを与えリードする指導者になっている。
農業の革新者
かつて、生産者という存在に過ぎなかった日本の農家世帯主の行動は、「経営者」と呼ぶに値せず「単なる業主」であると言われてきた(農業経済学者・東畑精一)。
ところで、食糧管理法は今から13年前の1995年まで存在した。戦時立法(1942年)である食管法は、高度経済成長の時代が過ぎ豊かな市場社会化が実現するだけでなく、コメの供給過剰が常態化した後も廃止されることはなかった。それは農業関係者の利権を維持するためであり、政治の手段だったからだ。農家が農業の「経営主体」になり得なかったのは農業政策の結果なのである。食管法が農家をマーケットから「隔離」し、顧客に出会うことを禁じてきたのである。
それに加えて様々な農家保護政策が彼らから自ら事業者としての自意識を育てるチャンスを奪った。また、多くの農民は、「経営者としての誇り」を自ら問うより、「被害者としての農民」という立場を声高に叫ぶ農業界のイデオロギーに安住する事大主義の中にいた。そして、本誌はそんな農家の存在を「自ら借金させられる農水省の作男」と揶揄してきた。
しかし、そんな時代の中でも顧客やマーケットを自覚す経営者たちは育っていた。そればかりでなく「土に戻し続ける」という農家としてのあるべき姿を追求する中で、「人と土」とのかかわりを「事業者と顧客」、「経営者と社会」に模して語れる農業経営者もいた。イノベーション(革新)をテーマにした今月号の特集に合わせて、すでに現役を引退されているが、筆者に本誌の創刊を動機付けた高松求(77歳)のことを紹介したい。高松の農業経営者としての人生こそ、農業の革新者そのものであると思うからだ。(以下つづく)
| 農業経営者取材 | 新・農業経営者ルポ | ||
第44回 危機を救ってくれたのは家族とお客様だけだった | 農業経営者 2月号 | (2008/02/01)
【(有)農作業互助会 代表取締役 鈴木博之(福島県大玉村)】
 1950年、福島県生まれ。1976年、機械の共同利用と作業請負をする任意団体を設立。1984年に(有)農作業互助会を法人化する。1988年に債務清算のため、資産が競売に掛けられそうになるが、農協を訴え、裁判所の和解勧告を得て危機を脱する。以後、コメの生産、集荷、小売事業で経営を再建。現在、低タンパク機能性米の商品開発を軸に、コメの付加価値化販売を図っている。コメの生産面積は自作地・借地含め約13ha。このほか約30haの作業請負を行なう。
1950年、福島県生まれ。1976年、機械の共同利用と作業請負をする任意団体を設立。1984年に(有)農作業互助会を法人化する。1988年に債務清算のため、資産が競売に掛けられそうになるが、農協を訴え、裁判所の和解勧告を得て危機を脱する。以後、コメの生産、集荷、小売事業で経営を再建。現在、低タンパク機能性米の商品開発を軸に、コメの付加価値化販売を図っている。コメの生産面積は自作地・借地含め約13ha。このほか約30haの作業請負を行なう。
経営破綻を乗り越えて
今から20年前の1988年、鈴木博之(57歳)は破産に陥る危機を経験している。76年に鈴木が中心となって組織した農業機械の共同利用と作業請負を目的とする任意団体「大山北部地区農作業互助会」が行き詰まった結果である。組織の機械導入のために、鈴木家の資産が担保になっていたのだ。その清算のための借金返済は、今も続いている。
任意団体の破綻に先立つ84年、鈴木は2農作業互助会を設立していた。鈴木博之・せつ子夫妻、そして川越尚治・志保子夫妻と二夫婦四人の法人である。現在は約13haでのコメ生産と販売、約30haの収穫調整を中心とした作業請負を行なっている。さらに07年12月には、2600万円を投資し、LGCソフトを原料米とする加工場と店舗を兼ねた団子屋を開店した。その加工場の責任者として、もう一夫婦を加えた三夫婦六人の経営に発展させようとしている。
任意団体の経営破綻。競売、裁判、和解勧告、そして経営再建への道のり。冷え切った村内での人間関係。その中で深まっていく家族の絆や、顧客や異業種の人々の支援……。
村社会、農協との軋轢の中での経営危機は、地域や親族を含む人間関係に悩むことでもあった。だが、そんな困難を経験すればこそ、鈴木は農民から本物の事業経営者に成長できたのだともいえる。
農協を訴える
農業高校を卒業して数年、鈴木は運送会社に勤めていた。しかし会社勤めを始めた父に代わり、23歳で農業を始めることになった。34年前のことだ。当時は3haの水田があれば、十分な収入になった。母と二人での稲作であり、田植えや収穫に人手を頼めば、持ち出しも大きくなっていった。若い鈴木はより発展的な農業をしたいと考えた。
機械化が飛躍的に進む時代だった。鈴木も機械化による省力を進めるとともに、作業請負の新事業に取り組みたいと考えた。
農協の勧めもあって、鈴木が農業機械の共同利用と作業請負を目的とする組織を作ったのは、76年のことだ。五戸の農家との共同事業だった。作業を受託する推進(営業)活動は、農協が担当することになっていた。コメの出荷も当然のことように農協だけだった。
しかし、やはり農協の勧めで組織された二つの受託集団との競合で、鈴木らの組織は経営が行き詰まることになる。鈴木ら以外の組織に仕事が流れ、鈴木の組織には仕事が回ってこないのだ。
「恨み言のように聞こえるかもしれないけど、ほかのグループの方が有力者との人脈が深く、農協の後押しが強かったのかもしれないですね。でも、今になって考えてみれば、他人に営業を任せて自分は仕事が来るのを待っているなんて、経営じゃないですよね」と鈴木は笑う。
売上が上がらない、人件費がかさむ、採算が取れない、返済ができない……。追加の融資、そしてその返済も滞り、借金はどんどん膨らんでいった。参加していたほかの農家は、農業をやめるといって組織を離れていった。残ったのは、鈴木と川越の二家族だけになった。
農協は組織の清算を要求し、担保設定されていた鈴木の家屋などを競売にかけると言ってきた。鈴木の親族や近隣の人々を含めて、落札予定者まで裏で話がついていた。その話を聞いて、鈴木は人生観が変わってしまうほどのショックを受けた。首をくくる者がいれば、その縄をなう人間もいるのが世の中なのだと、つくづく思い知らされた。
寝ても覚めても考えることは借金のことばかり。鈴木は当時を振りながら、今、困難の中にいる農業経営者に向けて伝えたいと言う。
「行き詰まった農家は、きっと農協の生命共済のことが頭にあると思う。自分もそうでした。農協とのかかわりが深ければ、5000〜6000万円くらいは共済がかかっているはず。自分もそれを考えながら、高速道路のガードレールに飛び込む夢を見ました。でも、その人なりの解決策は必ずあるんです。死を選ぶなんて、絶対すべきではありません。すべてが後ろ向きにしか物を考えられない時に、情緒的に振舞うことほどの不幸はありませんから。だから第一に、一人で悩まず、まず妻に、そして家族に現状を包み隠さず話すことが大事だと思います」
(以下つづく)
| 農業経営者取材 | 新・農業経営者ルポ | ||
第43回 家庭菜園が発掘したブラジル野菜市場 | 農業経営者 1月号 | (2008/01/01)
【C.A.H. 代表 林 治男(群馬県大泉町)】
 20年間のブラジル暮らしの後、帰国。趣味で始めた家庭菜園のブラジル野菜が職場の日系ブラジル人に好評を博す。あくまで友人へのおすそ分けとして始めたもの。しかし、林の野菜を求める日系ブラジル人があまりにも多く、断るつもりで野菜に値段をつけた。すると、逆に来訪者が一気に増え、専業のブラジル野菜生産者となる。現在、全国の約450店舗に出荷し、売り上げは月1000万円。
20年間のブラジル暮らしの後、帰国。趣味で始めた家庭菜園のブラジル野菜が職場の日系ブラジル人に好評を博す。あくまで友人へのおすそ分けとして始めたもの。しかし、林の野菜を求める日系ブラジル人があまりにも多く、断るつもりで野菜に値段をつけた。すると、逆に来訪者が一気に増え、専業のブラジル野菜生産者となる。現在、全国の約450店舗に出荷し、売り上げは月1000万円。
故郷の味を求める日系ブラジル人
現在、日本各地に暮らす日系ブラジル人は約30万人。その人たちが故郷で食べていた野菜や果物を日本国内で生産、供給している人がいる。群馬県大泉町を拠点に「C・A・H」という屋号でブラジル野菜を生産・出荷する林治男(60歳)である。出荷にあたってはブランド名として、蕫ブラジルの味﨟を意味するサボール・ブラジレイロという名称を使っている。全国450以上の店舗に届けられる作物の売り上げは、月平均約1000万円。出荷先はブラジル人向けのスーパーやブラジル料理店ばかりではなく、半分は一般のスーパーだという。
日系とはいえ数世代にわたってブラジルに暮らしてきた人々が慣れ親しんできた食材に対するニーズは大きく、生産力をはるかに超える需要がある。さらに、新しい食材に対する関心も高まっている。また、ブラジル野菜の多くはヨーロッパ諸国を原産とするものであり、ブラジル以外の外国人にも懐かしさを感じさせるものであるらしい。ところで、そんな林のブラジル野菜ビジネスは、日系人の妻や同じ職場で働く日系ブラジル人を喜ばせたいと、家庭菜園から始まったものである。 (以下つづく)
-
第3回 トマト編(その3) ハチとコナジラミに防虫ネットがオススメ…の巻 | 農業経営者 9月号 |(09/01)
- купить мдма(05/01)
- купить амфетамин(05/01)
- Vjrycs(05/01)
- Hrskvf(05/01)
- ThomasFrath(05/01)
- ライスショック(大きな国で)
- 何がどうおいしいを数字ではっきりと(花総果菜)
- 農業起業講座。(ほぼ日刊三浦タカヒロ。)
- 広島で屋上緑化かるいちばんとカルベラの展示です♪♪♪(Urban Green Life 街にもっと緑を・・・ 兼定興産の屋上緑化土「かるいちばん」)